「酢酸菌の事例からみる、日本の美食テック」に参加
- まこ
- 8月9日
- 読了時間: 7分
更新日:8月10日

2013年「和食」が日本人の伝統的な食文化としてユネスコに登録され国際的な認知度が広がってから早12年。現在では、腸内環境や免疫力改善が注目される中、納豆や味噌、漬物などの日本の発酵食品が世界で再評価されています。特に発酵食品が持つ自然な保存性や栄養価の高さが、健康志向の消費者に支持されていますよね。
そして現在、ある発酵食品が注目を集めています。それが『酢酸菌にごり酢』です。江戸時代の知恵による豊かな風味が、現代の科学により酢酸菌(さくさんきん)に様々な健康機能が解明され、食として新たな価値を生みだし注目されています。
酢酸菌にごり酢から日本の食文化の可能性を探る
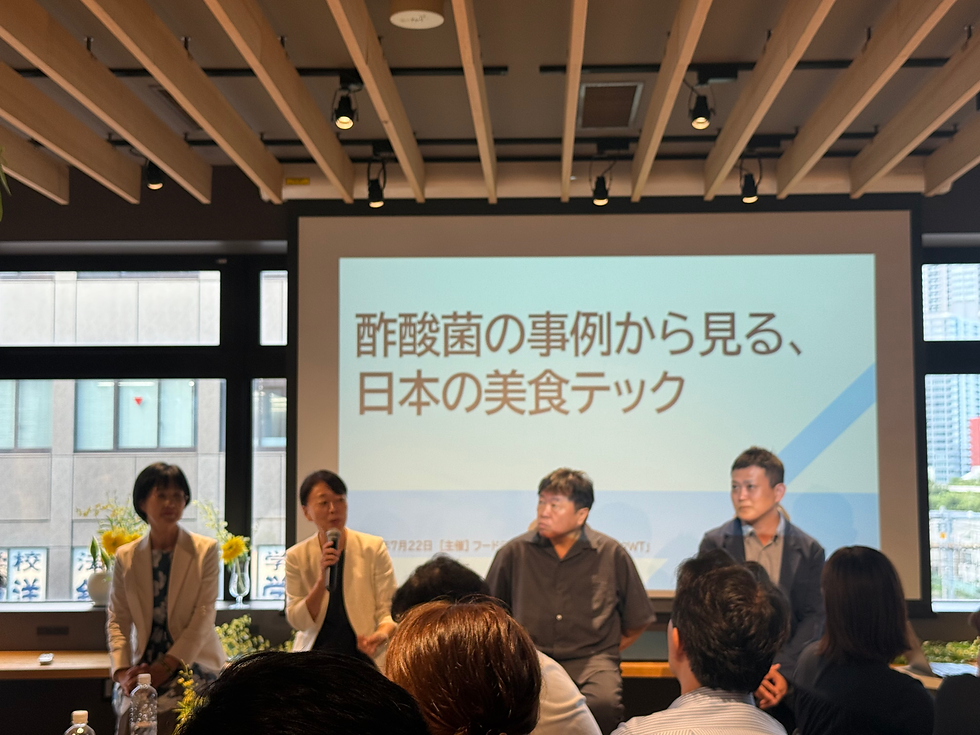
2025年7月22日、農林水産省「フードテック官民協議会」内に設置された「美食テックWT」が日本の食文化のさらなる発展を目指して「酢酸菌の事例からみる、日本の美食テック」が開催されました。登壇されたのは、アル・ケッチャーノオーナーの奥田政行シェフ、菊乃井常務取締役の堀知佐子さん、キューピー株式会社 免疫・認知プロジェクトの奥山洋平さんです。酢酸菌にごり酢を軸に日本が持つ食文化の可能性をどのように広げているのか、料理界と研究界の第一人者が集ったトークイベントの様子をお届けします。
奥田政行シェフ「ガストロノミーとは、単なる料理技術の話ではなく、人や土地の記憶を呼び起こすストーリーだ」

奥田政行シェフは、山形県鶴岡市にて「アル・ケッチァーノ」を主宰し、地元食材の価値を世界に発信する料理人です。今回の講演では、彼が提唱する「ガストロノミーツーリズム」の本質と、地域の食材に命を吹き込む料理のあり方が熱く語られました。奥田シェフは冒頭、「ガストロノミーとは、単なる料理技術の話ではなく、人や土地の記憶を呼び起こすストーリーだ」と定義づけ、スライドを交えながら、実際の体験談を披露しました。特に印象的だったのが、地元の羊肉との出会いです。ある日、常連客から手渡された地元産の羊肉を生で口にした瞬間、その圧倒的な旨味と臭みのなさに感動。「この肉だけで成立する味」と直感し、すぐに生産者・丸山氏の羊舎を訪ね、飼育環境・餌・生産者の哲学を徹底的に学びました。
この出会いを無駄にしたくないと考えた奥田シェフは、東京の有名レストランやメディアに飛び込み営業を実施。羊肉を試食させると、有名シェフたちが口を揃えて驚き、その評判はすぐに専門誌やグルメ雑誌に掲載され、やがて「庄内羊」は一大ブームとなりました。奥田シェフは「味の記憶をつくるのは、一人の料理人と一人の生産者の情熱から始まる」と語り、その熱意が地元の農業者の誇りをも取り戻したことを強調しました。さらに、藤沢カブや庄内豚といった地場食材を主役にした料理開発についても詳細に解説。藤沢カブは、絶滅の危機にあった在来種を地元の生産者とともに復活させ、スライドで紹介された「藤沢カブと庄内豚の焼畑見立て」は、20年以上経った今も観光客や食通を惹きつけ続ける代表作となっています。
奥田シェフの言葉で印象的だったのは、「売れるポイントは、地球上に一つしかない圧倒的な味だ。ありふれたものを作っていては、人の心を動かすことはできない」というものです。
講演の後半では、味の理論構築について語りました。母乳の甘味・油・塩・旨味・酸味・香り・喉ごし・フレッシュ感など、人が本能的に「もう一度食べたい」と思う要素を体系化し、それらを複合的に組み立てることで、食べ飽きない料理が生まれると解説。さらに、旨味と酸味を両立させる新しい調理法として「酢酸菌にごり酢」の活用例を提示し、寿司酢への応用で深みのある味を実現できることを紹介しました。
「料理は味だけではなく、地域の物語を世界に届ける手段である。私のゴールは、庄内を食で訪れる街にすることだ」と、ガストロノミーの未来像を語りました。
ライター木村コメント
「ガストロノミー」という視点から見ると、日本の発酵文化は単なる調理法ではなく、歴史、気候、微生物、人との関係性までを含む総合的な食文化として高く評価されていることがわかります。デンマークのレストラン「Noma」では、日本の発酵技術を導入したガストロノミー体験を提供するなど、世界的に発酵への関心の高さが伺えます。「伝統的和食型」の食生活が健康寿命を延ばす

堀知佐子シェフは、和食の健康価値と発酵文化の可能性について、科学的根拠をもとに解説しました。堀シェフは京都「菊乃井」で長年にわたり食文化を支え、現在は東京・赤坂「ルリール」を経営。さらに通販ブランド「ちさこ食堂」を立ち上げ、家庭でも本格的な和食を楽しめる取り組みを展開しています。
講演の前半では、和食の歴史的背景と栄養学的評価に触れました。和食は2013年にユネスコ無形文化遺産に登録され、多様な食材、季節感、行事との結びつきといった文化的価値を持ちます。栄養面でも、「食物繊維 × 発酵」をキーワードに、腸内環境を良好に保つ役割があると指摘しました。
スライドでは、国立がん研究センターの多目的コホート研究(2020年)やNutrition Journal(2017年)のデータを紹介。「伝統的和食型」の食生活を続ける人々は、全死亡リスクが14%、心疾患死亡リスクが11%低下するという統計が示されました。
堀シェフは、「健康をつくるのは難しいことではなく、日々の食事の積み重ね」と述べ、味噌汁、海藻、漬物、緑黄色野菜、魚介類といった和食要素の効用を再評価。中でも酢酸菌を含む「にごり酢」は、旨味成分が豊富で減塩にもつながり、和食の調味料として理想的と語りました。
また、腸活の観点から、発酵食品と食物繊維の組み合わせが重要であることを説明。腸内の善玉菌が食物繊維をエサに短鎖脂肪酸を生成し、腸内を酸性に保つことで悪玉菌が減少し、腸内環境が整うというメカニズムを図解付きで紹介しました。
「食は体を作るだけでなく、心を癒し、家族や地域の絆を強めるもの」と述べ、料理人として「心の栄養」を提供することの大切さを強調しました。
講演の最後には、「和食を少しずつでも取り入れられれば、日々の健康は難しくないと」語りました。
ライター木村コメント
日本の伝統的な食事スタイルの一汁三菜主食(汁物1品、おかず3品(主菜1品+副菜2品))が理想ですが、一汁二菜でも十分に栄養素が摂れるのが和食だと話されていました。忙しい人は毎日、味噌汁だけでも良いですね。また、塩味が足りない時は酢を足すと味が整うとシェフ目線の話が勉強になりました。酢酸菌で現代人が抱える
4大不調(風邪や花粉症、疲労感、倦怠感)への有効性を実証

奥山洋平氏は、酢酸菌研究と「酢酸菌にごり酢」の開発背景を詳しく解説しました。キユーピーは1962年に「キユーピー醸造」を設立し、西洋酢の製造技術を国内で先駆的に確立。奥山氏は、「江戸時代のお酢は粗ろ過のため酢酸菌が豊富に残っており、それが旨味と健康効果を支えていた」と指摘し、この製法を現代に復活させたのが「酢酸菌にごり酢」であると説明しました。
スライドでは、酢酸菌の健康効果を裏付けるデータが多数提示されました。特に、免疫の司令塔であるpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)を活性化し、免疫バランスを整える作用が臨床試験で確認されたことを紹介。風邪や花粉症、疲労感、倦怠感など、現代人が抱える4大不調への有効性が実証されています。
また、乳酸菌や納豆菌との相乗効果も報告されており、アレルギー症状の軽減に貢献することがわかっています。
腸活への影響については、4週間の摂取試験において、排便回数・便性状・便量が有意に改善された結果が示され、「にごり酢が腸を良い状態へ導く」と解説しました。
さらに、味覚センサー「レオ」による分析結果も披露。「酢酸菌にごり酢は0.2ポイントの差でも95%の人が味の違いを感じるほど、旨味と酸味が強調された“うま酸っぱい”味」と評価され、昆布だしと同レベルの旨味が確認されたといいます。
「11月25日を『いいにごり酢の日』として制定し、全国の蔵元と連携しながら、日本の食文化の新しい価値を創造していきたい」と述べ、酢酸菌を中心に据えた未来型フードテック戦略を提示しました。

ライター木村コメント
酢酸菌を使った発酵食品には米酢、黒酢、バルサミコ酢をはじめ、コンブチャやフルーツ酢があります。ライフスタイルに合わせて、手軽に取り入れられるものからはじめてみるのが良いですね。
日本の発酵技術は「健康」、「サステナブル」、「味覚の革新」、「文化の継承」といった現代社会のテーマと深く結びついていることがわかります。今後も『酢酸菌にごり酢』の可能性に注目していきたいです。



コメント